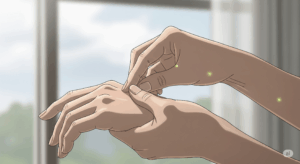頭痛と耳鳴りが同時に起こると、多くの方が「何か重大な病気ではないか?」と強い不安を感じることでしょう。
これらの症状は私たちの日常生活の質を大きく低下させ、時には集中力の著しい低下や気分の落ち込み、さらには日常生活への支障にも繋がりかねません。
本記事では、頭痛と耳鳴りが同時に発生する主な原因から、ご自身で試すことができる効果的な応急処置やセルフケア、そして日頃から意識して取り組める予防策に至るまで、医学的な専門知識がない方にも分かりやすく、具体的な情報をお届けします。
つらい症状への理解を深め、適切な行動をとるための一助となれば幸いです。
1. 頭痛と耳鳴りが同時に起こる主な原因と見逃せない危険なサイン
頭痛と耳鳴りが一緒に現れたとき、多くの方がまず知りたいのは「なぜこのような症状が出るのだろうか?」そして「このまま様子を見ていても大丈夫なのだろうか?」ということでしょう。
この章では、考えられる主な原因と、特に見過ごしてはいけない危険な兆候について、具体的な例を交えながら詳しくご説明します。
ご自身だけで判断するのは非常に危険ですが、正しい知識を持つことで、いざという時に冷静に、そして適切に対処できるようになります。
1-1. 最も一般的な原因:肩や首の凝り、そして精神的なストレスの影響
頭痛と耳鳴りが同時に起こる原因として、私たちの日常生活の中で非常に多く見られるのが、肩こりや首こり、そして精神的なストレスです。これらは現代人にとって切っても切り離せない問題と言えるかもしれません。
例えば、毎日長時間にわたってパソコンに向かってデスクワークをする、スマートフォンをうつむいた姿勢で長時間使い続ける、あるいは無意識のうちに猫背が癖になっているといったことはありませんか。これらの良くない姿勢や習慣は、首や肩周りの筋肉に、自分では気づかないうちに過度な負担をかけ続け、筋肉をガチガチに緊張させてしまいます。
この筋肉の緊張が慢性的に続くと、その部分の血流が悪化し、頭部へ酸素や栄養が十分に行き渡らなくなってしまいます。その直接的な結果として、頭全体が締め付けられるような、あるいは重苦しい不快感を伴う「緊張型頭痛」と呼ばれるタイプの頭痛が引き起こされることがあります。
さらに、首周りの筋肉の過度な緊張は、耳のすぐ近くを通っている細い血管や繊細な神経にも悪影響を及ぼし、耳周辺の血流を著しく悪化させることがあります。これが原因となって、「キーン」というような甲高い音の耳鳴りや、「ジー」「ザー」といった比較的低い音の耳鳴りが発生することがあるのです。
また、職場での仕事のプレッシャー、複雑な人間関係の悩み、家庭環境の大きな変化など、精神的なストレスも、頭痛や耳鳴りを引き起こす非常に大きな要因となります。ストレスを感じると、私たちの体は無意識のうちに「自律神経」という体の様々な機能を自動的に調整してくれているシステムのバランスを崩してしまいます。
自律神経が乱れると、血管の収縮や拡張を適切にコントロールできなくなり、その結果として頭痛が悪化したり、耳鳴りがより強く感じられたりすることがあります。これらの原因は、日々の生活習慣と深く結びついているため、もし思い当たる節がある方は、まずご自身の生活習慣を丁寧に見直すことから始めてみましょう。
自律神経とは? 詳細解説
自律神経は、私たちの意思とは全く関係なく、生命を維持するために必要な体の働き、例えば呼吸の仕方、心臓の鼓動の速さ、血圧の調整、体温の維持、食べ物の消化や栄養の代謝といった機能を、24時間休むことなく自動的にコントロールしている非常に重要な神経システムです。
この自律神経には、主に体を活動的にする時に働く「交感神経」と、体をリラックスさせる時に働く「副交感神経」という2つの種類があり、これらがお互いにシーソーのようにバランスを取り合うことで、私たちの体の調和が保たれています。
しかし、過度な精神的ストレス、不規則な生活リズム、慢性的な睡眠不足などが続くと、この大切な自律神経のバランスが崩れてしまい、その結果として頭痛、めまい、動悸、消化不良、気分の落ち込みといった、様々な心や体の不調が現れやすくなるのです。
1-2. 放置は危険!重篤な病気の可能性と見逃してはいけない緊急サイン
頭痛や耳鳴りは、誰でも一度は経験するようなありふれた症状だからと、安易に軽く考えてはいけません。時には、迅速かつ適切な医療対応が求められる重大な病気が背景に隠れているサインである可能性も否定できないのです。
特に警戒が必要なのは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血といった、いわゆる「脳血管障害」と呼ばれる一連の病気です。これらの病気は、脳の血管が詰まってしまったり(脳梗塞)、破れてしまったり(脳出血、くも膜下出血)することで、脳細胞が深刻なダメージを受け、最悪の場合、命に関わることもある非常に危険な状態を引き起こします。
脳血管障害の初期症状として、頭痛や耳鳴りが現れることがあり、以下のような特徴的なサインが見られたら、絶対に放置せず、直ちに医療機関を受診するか救急車を呼んでください。
- これまでに経験したことのないような、突然の激しい頭痛(よく「金属バットやハンマーで殴られたような痛み」と表現されます)
- ろれつが回らない、言葉がうまく出てこない、他人の言うことが理解できない
- 片方の手足がしびれる、力が入らない、麻痺して動かせない
- 顔の半分が歪んで見える、口角が片方だけ下がる、食べ物や飲み物が口からこぼれる
- 物が二重に見える、視野の一部が欠けて見える、片方の目が見えにくい
- 意識がもうろうとする、呼びかけに対する反応が鈍い、眠り込んでしまう
- 立っていられないほどの強いめまい、吐き気や嘔吐を伴うめまい
- 突然のけいれん発作
また、耳鳴りに関しては、「突発性難聴」や「メニエール病」といった耳自体の病気が原因である場合、できるだけ早く専門的な治療を開始することが、聴力の回復に大きく影響します。治療開始が遅れるほど、聴力が元に戻りにくくなる可能性があります。
「突発性難聴」は、文字通りある日突然、主に片方の耳が聞こえにくくなったり、全く聞こえなくなったりする病気で、耳鳴りやめまいを伴うことも少なくありません。「メニエール病」は、周囲がぐるぐる回るような激しい回転性のめまい、聞こえたり聞こえにくくなったりを繰り返す変動する難聴(特に低い音域の音が聞こえにくくなることが多いです)、耳鳴り、耳が詰まった感じ(耳閉感)といった症状が、発作的に繰り返されるのが特徴的な病気です。これらの症状に加えて、原因不明の高熱や、何度も繰り返す嘔吐が続く場合も、速やかな医療機関の受診が必要です。
脳血管障害の危険性について
脳血管障害は、時間との勝負です。症状が現れてから治療開始までの時間が短いほど、後遺症が軽くなる可能性が高まります。
特に「ハンマーで殴られたような」と表現される激しい頭痛は、くも膜下出血の典型的な症状であり、命に直結する極めて危険なサインです。迷わず救急車を呼んでください。
家族や周囲の人がこれらのサインに気づいた場合も、ためらわずに救急対応をすることが重要です。
1-3. 自己判断は禁物!医療機関を受診すべき具体的な症状とタイミング
頭痛と耳鳴りが同時に現れたとき、「このくらいの症状なら大丈夫だろう」「少し休めば治るだろう」と自分で判断してしまうのは非常に危険です。なぜなら、その背後には深刻な病気が隠れている可能性があるからです。
では、具体的にどのような症状が見られたら医療機関を受診すべきなのでしょうか。まず、「これまでに経験したことのないような激しい頭痛」や、「突然発症した今までとは違う性質の頭痛」の場合は、迷わずすぐに医療機関を受診してください。特に、前述したようにバットで殴られたような痛みと表現されるような強烈な頭痛は、くも膜下出血の典型的な症状であり、一刻を争う緊急事態です。
また、頭痛や耳鳴りに加えて、以下のような神経に関連する症状を伴う場合も、緊急性が高いと考えられますので、直ちに医療機関への連絡が必要です。
- めまい(特に、自分や周囲がぐるぐる回るような回転性で、立っていられないほど強いもの)
- 吐き気、嘔吐(特に、頭痛がひどくなるにつれて現れるものや、噴水のように突然吐くもの)
- 手足のしびれ、麻痺(体の片側だけに出る場合や、徐々に範囲が広がる場合など)
- ろれつが回らない、言葉が出にくい、思ったように話せない
- 物が二重に見える、視野の一部が欠けている、普段と見え方が明らかに違う
- 意識がもうろうとする、呼びかけへの反応が鈍い、簡単な質問に答えられない
耳鳴りに関しては、片方の耳だけに急に起こった場合や、耳鳴りの音の大きさや種類が徐々に大きくなっている、あるいは変化している場合、聞こえにくさ(難聴)を伴う場合は、耳鼻咽喉科の専門医の診察が必要です。これらの症状は、突発性難聴やメニエール病、あるいは稀ですが聴神経腫瘍などの可能性も考えられます。
症状が数日以上続いている場合や、市販の鎮痛薬を服用しても全く改善が見られない、あるいはむしろ悪化するような場合も、原因を特定し適切な治療を受けるために医療機関を受診することを強くお勧めします。受診のタイミングとしては、これらの危険なサインが見られた場合は直ちに救急車を呼ぶか、夜間・休日であれば救急外来を受診してください。それ以外の場合でも、症状が気になり始めたらできるだけ早めに、まずはかかりつけ医に相談するか、症状に応じて耳鼻咽喉科、脳神経外科、神経内科など、適切な診療科を受診することを検討しましょう。
受診する診療科の目安
どの科を受診すればよいか迷う場合、以下を目安にしてください。
・耳鼻咽喉科: 耳鳴り、めまい、難聴が主な症状の場合。突発性難聴やメニエール病が疑われる場合。
・脳神経外科・神経内科: 激しい頭痛、ろれつが回らない、手足の麻痺など、脳の異常が疑われる症状がある場合。くも膜下出血、脳梗塞、脳出血などが疑われる場合。
・内科・総合診療科: まずは相談したい場合や、どの科か判断が難しい場合。高血圧など内科的な要因が考えられる場合。
迷ったら、まずはかかりつけ医に相談するか、医療機関の相談窓口に問い合わせてみるのが良いでしょう。
2. すぐに試せる!頭痛と耳鳴りの応急処置とセルフケア
突然の頭痛や耳鳴りに襲われた時、すぐに医療機関を受診できない状況や、日常生活の中で少しでも症状を和らげたいと思うのは自然なことです。
この章では、ご自身ですぐに試すことができる応急処置や、日頃から生活に取り入れやすいセルフケアの方法について、具体的な手順や実践する際のポイントを交えながら詳しく解説します。
ただし、これらの方法はあくまで一時的な症状の緩和を目的としたものであり、症状が継続する場合や悪化する兆候が見られる場合は、自己判断せずに必ず専門医の診断を受けるようにしてください。
2-1. 安静とリラックス:具体的な環境作りとおすすめの体勢
頭痛や耳鳴りが生じた際は、まず無理をせず安静にすることが最も重要です。活動を続けると症状が悪化する可能性があります。
騒がしい場所や、明るすぎる照明、チカチカする光などは症状を悪化させることがあるため、できる限り静かで落ち着ける環境を確保しましょう。可能であれば、横になって目を閉じ、深呼吸を繰り返すことで心身のリラックスを促します。
深呼吸は、例えば、まず4秒かけてゆっくりと鼻から息を吸い込み、次に2秒程度息を止め、その後6~8秒かけてゆっくりと口から息を吐き出す、というリズムで行うと効果的です。これにより、リラックス効果のある「副交感神経」が優位になり、血管の過度な緊張を和らげる効果が期待できます。
部屋の温度や湿度も、自分が最も快適だと感じる状態に調整しましょう。暑すぎたり寒すぎたりすると、それ自体がストレスとなり得ます。また、リラックスできる静かな音楽を小さな音量で流したり、ラベンダーやカモミールといった鎮静効果のあるアロマオイルをティッシュペーパーに数滴垂らして枕元に置いたりするのも良いでしょう。ただし、香りが強すぎるとかえって気分が悪くなることもあるので、ほのかに香る程度に調整してください。
体勢としては、仰向けで寝るのが一般的ですが、その際に枕の高さが非常に重要です。枕が高すぎると首が前に突き出る形になり、低すぎると頭が下がりすぎてしまい、どちらも首に大きな負担がかかり、症状を悪化させる可能性があります。
首の自然なカーブ(頚椎前弯)を保てるように、バスタオルを数回丸めて自分の首の高さに合うように調整し、首の後ろに置いたり、首の形にフィットするように設計された体圧分散型の枕を選んだりするのも有効です。横向きで寝る場合は、抱き枕などを利用して体が安定するように工夫し、下になっている方の肩や腕に体重がかかりすぎないように注意しましょう。
快適な安静環境を作るための追加のヒント
・光の遮断: アイマスクを使用したり、遮光カーテンを閉めたりして、目に入る光をできるだけ減らしましょう。特に片頭痛の場合、光に過敏になることが多いです。
・音の遮断: 耳栓を使用したり、ホワイトノイズマシン(単調な音を出す機械)を使ったりして、気になる騒音を遮断するのも有効です。ただし、耳鳴りの場合は完全に無音にするとかえって耳鳴りが気になりやすくなることもあるため、小さな環境音はあっても良いでしょう。
・衣服の調整: 体を締め付けるような窮屈な衣服は避け、ゆったりとした楽な服装に着替えましょう。ベルトやネクタイなども緩めるのがおすすめです。
2-2. 首・肩の緊張緩和:簡単なストレッチとマッサージの方法
頭痛や耳鳴りの一般的な原因の一つである首や肩の凝りを和らげるためには、適度なストレッチやセルフマッサージが有効です。ただし、痛みが非常に強いときや、炎症が起きている(熱感がある、腫れているなど)ときは無理に行わず、症状を悪化させないように細心の注意を払ってください。
ここでは、座ったままでもオフィスや自宅で簡単にできるストレッチとセルフマッサージの方法をご紹介します。
- 首のストレッチ
- まず、椅子に深く座り、背筋を軽く伸ばします。ゆっくりと首を前に倒し、あごを胸につけるようなイメージで、首の後ろが心地よく伸びるのを感じながら15秒程度キープします。
- 次に、ゆっくりと首を後ろに倒し、天井を見上げるようにして15秒程度キープします。この時、首の後ろに痛みや違和感がある場合は無理せず、可動域を狭めてください。
- 首を右にゆっくりと倒し、右耳を右肩に近づけるようなイメージで、首の左側を伸ばして15秒程度キープします。この時、左手でそっと頭の左側頭部を押さえると、より効果的にストレッチできます。反対側(左に倒す)も同様に行います。
- 最後に、首を右にゆっくりと回し(右後方を振り向くように)、あごを右肩に近づけるようなイメージで15秒程度キープします。反対側(左に回す)も同様に行います。すべての動作は、反動をつけず、ゆっくりと行うことがポイントです。
- 肩のストレッチ
- 両肩を耳に近づけるようにゆっくりと力強くすくめ、数秒間その状態をキープした後に、ストンと力を抜いて肩を下ろします。これを数回繰り返します。肩周りの筋肉が温まるのを感じましょう。
- 両腕を体の前で組み、手のひらを外側に向けます。そのまま背中を丸めながら腕を前方にぐーっと伸ばし、肩甲骨の間(背中の中央上部)を広げるように意識して15秒程度キープします。
- 今度は両腕を背中の後ろで組みます。可能な範囲で肘を伸ばし、胸を張るようにしながら肩甲骨を中央に寄せ、15秒程度キープします。
- セルフマッサージ
指の腹(指紋のある部分)を使って、首筋(特に髪の生え際から肩にかけての部分)や、肩の凝っていると感じる部分を、痛気持ちいいと感じる程度の強さで優しく揉みほぐします。強く押しすぎたり、グリグリと力を入れすぎたりすると、かえって筋肉を傷めることがあるので注意が必要です。
特に、耳の後ろの出っ張った骨(乳様突起)から鎖骨の内側にかけて斜めに伸びる「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」や、首の付け根のくぼみ(風池:ふうち、天柱:てんちゅうといったツボがあるあたり)周辺を重点的に行うと良いでしょう。蒸しタオルなどで首や肩を事前に温めながら行うと、血行が促進され、リラックス効果がさらに高まります。
これらのストレッチやマッサージは、仕事の合間や休憩時間など、気づいた時にこまめに行うことで、凝りの蓄積を防ぐ効果も期待できます。
胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)とは?
胸鎖乳突筋は、耳の後ろにある骨(乳様突起:にゅうようとっき)から始まり、首の前を下って鎖骨の内側と胸骨の上部に付着している、首の側面にある太くて長い筋肉です。
首を横に曲げたり、顔を左右に回したりする際に主に働く重要な筋肉ですが、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などで前かがみの姿勢が続くと、この筋肉が過度に緊張しやすくなります。胸鎖乳突筋の緊張は、頭痛(特に側頭部や後頭部の痛み)、めまい、耳鳴り、吐き気などの原因になることもありますので、優しくほぐすことが大切です。
2-3. 市販薬の服用:注意点と症状を悪化させないためのポイント
我慢できないほどのつらい頭痛が急に起きた場合、市販の鎮痛薬を服用することも、症状を一時的に和らげるための一つの選択肢となります。しかし、薬の選択や使用方法にはいくつかの重要な注意点がありますので、これらを必ず守るようにしてください。
まず、ご自身の症状(ズキズキする痛みか、締め付けられるような痛みかなど)や体質(アレルギー歴、胃腸の強さなど)に合った薬を選ぶことが非常に大切です。市販の鎮痛薬には、アセトアミノフェン、イブプロフェン、ロキソプロフェンナトリウム水和物など、様々な有効成分が含まれており、それぞれ特徴や副作用のリスクが異なります。どの成分が自分に適しているか分からない場合は、自己判断せず、薬局の薬剤師や登録販売者に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
薬を服用する際は、できる限り空腹時を避け、コップ一杯程度の水またはぬるま湯で、必ず用法・用量を守ることが重要です。効果を期待して一度に多くの量を飲んだり、指定された服用間隔よりも短い時間で再度服用したりすることは絶対に避けてください。特に注意が必要なのは、鎮痛薬の使いすぎです。鎮痛薬をあまりにも頻繁に(例えば、月に10日以上、あるいは週に2~3日以上)服用し続けると、かえって頭痛を悪化させてしまう「薬物乱用頭痛(やくぶつらんようずつう)」という非常に厄介な状態を引き起こす可能性があります。
この薬物乱用頭痛になると、薬が効きにくくなるだけでなく、薬が切れるとリバウンドのように頭痛が起こるという悪循環に陥ってしまい、治療が難しくなることがあります。耳鳴りに対しては、残念ながら現在のところ、市販薬で直接的な効果が科学的に証明されているものは非常に少ないのが現状です。血行を促進する成分やビタミン剤などが配合されたものもありますが、その効果には個人差が大きく、全ての人に有効とは限りません。
市販薬を数回服用しても症状が全く改善しない場合や、むしろ悪化するような場合には、自己判断を続けずに速やかに医療機関を受診し、根本的な原因を特定して適切な治療を受けることが最も大切です。
薬剤師への相談のポイント
市販薬を選ぶ際に薬剤師に相談する時は、以下の情報を伝えると、より適切なアドバイスを受けやすくなります。
・いつから、どのような頭痛か (ズキズキ、締め付けられる、ガンガンするなど)
・他に症状はあるか (耳鳴り、めまい、吐き気、発熱など)
・現在治療中の病気や服用中の薬はあるか (お薬手帳があれば持参しましょう)
・アレルギー歴や副作用の経験はあるか
・妊娠中・授乳中ではないか
これらの情報を元に、薬剤師が最適な薬を選んでくれます。
3. 頭痛と耳鳴りを引き起こす可能性のある代表的な病気
頭痛と耳鳴りが同時に現れる場合、単にその時の体調が優れないというだけでなく、特定の病気が背景に潜んでいることがあります。
この章では、そのような症状を引き起こす可能性のある代表的な病気について、それぞれの特徴や注意すべき点を詳しく解説します。
病気に関する正しい知識を持つことは、早期発見・早期治療に繋がり、重症化を防ぐために非常に重要です。
3-1. メニエール病:回転性のめまいや難聴を伴う特徴と初期症状
メニエール病は、耳の最も奥にある「内耳(ないじ)」という部分の液体(リンパ液)の圧力バランスが崩れ、内耳の中に異常にリンパ液が増えてしまうこと(内リンパ水腫:ないりんぱすいしゅ と呼ばれます)が原因で起こると考えられている病気です。内耳は音を感じ取る蝸牛(かぎゅう)と体のバランスを司る三半規管(さんはんきかん)・耳石器(じせきき)から構成されています。
この病気の主な症状は、以下の3つが特徴的で、これらがセットで、あるいは時間差で現れ、発作的に、そして何度も繰り返されます。
- 回転性のめまい: 自分自身や周囲の景色がぐるぐる回るような、時には立っていられないほどの激しいめまいが突然起こります。このめまいは通常、数十分から数時間続くことが多いですが、数日に及ぶことも稀にあります。めまい発作中は吐き気や嘔吐、冷や汗などを伴うことも少なくありません。
- 難聴: 特に低い音域の音が聞こえにくくなることが多く、聴力はめまい発作のたびに良くなったり悪くなったりと変動したり、発作を繰り返すうちに徐々に悪化したりすることがあります。片耳だけに起こることが多いですが、両耳に起こることもあります。
- 耳鳴り: 「ザーザー」「ゴーゴー」といった低い音の耳鳴りが特徴的で、めまいの前兆として現れたり、めまい発作中に特に強くなったりすることがあります。音が割れて聞こえるように感じることもあります。
これらに加えて、耳が詰まったような感じ(耳閉感:じへいかん)や、自分の声が大きく響く感じ(自声強聴:じせいきょうちょう)を伴うこともあります。頭痛はメニエール病の典型的な主症状ではありませんが、激しいめまい発作による身体的・精神的なストレスや、それに伴う自律神経の乱れから、二次的に頭痛(特に肩こりなどからくる緊張型頭痛)を併発するケースが見られます。
メニエール病は、過度なストレスや慢性的な疲労、睡眠不足、気圧の急激な変化などが発作の誘因となることが多いと言われています。そのため、薬物療法(利尿薬、抗めまい薬、循環改善薬、ステロイドなど)による治療だけでなく、生活習慣の改善(十分な睡眠、ストレス管理、塩分を控えた食事など)も治療の重要な柱となります。
もし、上記のような症状が繰り返し起こる場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査や平衡機能検査など専門的な検査を受けて、適切な診断と治療を開始することが大切です。早期の対応が、症状のコントロールや聴力の維持に繋がります。
内耳(ないじ)の構造と役割
内耳は、側頭骨の中にある非常に複雑な構造をした器官で、主に「蝸牛(かぎゅう)」と「前庭(ぜんてい)」という部分から成り立っています。
・蝸牛:カタツムリの殻のような形をしており、内部には音を感じ取るための有毛細胞(ゆうもうさいぼう)があります。中耳から伝わってきた音の振動を電気信号に変換し、聴神経を介して脳に伝える役割を担っています。
・前庭:三半規管と耳石器(卵形嚢・球形嚢)から構成され、体の回転運動や直線加速度、重力などを感知し、体のバランス(平衡感覚)を保つ役割を担っています。
メニエール病では、この内耳のリンパ液の過剰な貯留により、蝸牛や前庭の機能が障害されることで、難聴、耳鳴り、めまいといった症状が現れると考えられています。
3-2. 突発性難聴:突然の聞こえにくさと耳鳴り、頭痛が生じるメカニズム
突発性難聴は、その名の通り、ある日突然、何の予兆もなく、片方の耳(稀に両方の耳)の聴力が急激に低下する病気です。例えば、「朝起きたら片方の耳が聞こえなくなっていた」「電話の音が片方の耳だけ全く聞こえない」といった形で発症することが多いのが特徴です。
原因はまだ完全には解明されていませんが、有力な説としては、内耳の血流障害(血液循環の悪化)、ウイルス感染(おたふくかぜウイルスやヘルペスウイルスなど)、過度なストレスや疲労、自己免疫疾患などが関与しているのではないかと考えられています。これらの要因が複合的に影響し合って発症するとも言われています。
主な症状は、急激に起こる難聴の他に、耳鳴り(多くの場合、難聴のある耳に起こります)、めまい(ぐるぐる回る回転性めまいや、フワフワするような浮動性めまい)、耳が詰まった感じ(耳閉感)を伴うことがあります。突発性難聴で起こる耳鳴りは、「キーン」「ピー」といった金属音のような高い音や、「ジー」といった蝉の鳴き声のような音が比較的多いとされていますが、低い音の耳鳴り(「ボー」「ゴー」など)の場合もあります。一般的に、難聴の程度が強いほど、耳鳴りも強く感じられる傾向があります。
頭痛は突発性難聴の直接的な主要症状ではありませんが、突然の聴力低下というショッキングな出来事や、不快な耳鳴りが続くことによる精神的なストレスや強い不安感、あるいはめまいを伴うことによる身体的な負担から、二次的に緊張型頭痛などを引き起こすことがあります。
突発性難聴は、発症後できるだけ早期(理想的には1週間以内、遅くとも2週間以内)に専門的な治療を開始することが、聴力回復のために非常に重要であるとされています。治療開始が遅れると、聴力が十分に回復しにくくなったり、最悪の場合、後遺症として難聴や耳鳴りが永続的に残ってしまったりする可能性が高まります。治療は、副腎皮質ステロイド薬の投与(内服や点滴)、血管拡張薬、ビタミンB12製剤、代謝賦活薬などが用いられるほか、高気圧酸素療法などが行われることもあります。
突発性難聴の早期受診の重要性
突発性難聴の治療は時間との戦いです。「そのうち治るだろう」と安易に考えず、症状に気づいたらすぐに耳鼻咽喉科を受診しましょう。
特に、以下の場合は緊急性が高いと考えられます。
・全く聞こえなくなった、または著しく聞こえにくい。
・強いめまいを伴う。
・両耳に症状がある(非常に稀ですが重篤な場合があります)。
治療開始が早ければ早いほど、聴力回復の可能性が高まります。
3-3. 脳血管障害(脳梗塞・脳出血など):命に関わる初期症状と見分け方
脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの「脳血管障害」は、脳の血管が詰まってしまったり(脳梗塞)、破れてしまったり(脳出血、くも膜下出血)することで、脳細胞に酸素や栄養が適切に供給されなくなり、その結果、脳の機能が広範囲にわたって損なわれる、命に関わる緊急性の非常に高い病気です。これらの病気は、一刻も早い診断と治療がその後の経過を大きく左右します。
これらの病気の初期症状として、頭痛と耳鳴りが現れることがあります。特に注意すべき頭痛は、「これまでに経験したことのないような尋常ではない激しい頭痛」や、「突然バットで殴られたような痛み」「頭の中で何かが破裂したような痛み」と表現されるような、突発的で非常に強いものです。特にくも膜下出血では、このような特徴的な頭痛が典型的な症状として知られています。脳梗塞や脳出血でも、頭痛の程度や性質は様々ですが、普段経験するような一般的な頭痛とは異なる性質(例えば、徐々に痛みが強くなっていく、特定の体勢で痛みが強くなる、嘔吐を伴うなど)を持つことがあります。
耳鳴りに関しては、脳の中でも聴覚や平衡感覚に深く関わる「脳幹(のうかん)」や「小脳(しょうのう)」といった部分の血管に障害が起きた場合に、めまいと共に突然現れることがあります。この場合の耳鳴りは、他の症状(呂律が回らない、物が二重に見えるなど)を伴うことが多いです。
これらの頭痛や耳鳴りに加えて、以下のうち一つでも当てはまる症状が見られた場合は、脳血管障害の可能性が非常に高いため、一刻も早く救急車を要請し、専門的な医療機関(脳神経外科や神経内科のある病院)を受診する必要があります。
- F (Face:顔の麻痺): 「イー」と口を横に開いたときに、顔の片側が歪んでしまう、口角がうまく上がらない、片方の目が閉じにくい。
- A (Arm:腕の麻痺): 両腕を肩の高さまで前に伸ばしたときに、片方の腕が力なく下がってくる、または全く上がらない。
- S (Speech:言葉の障害): ろれつが回らない(何を言っているか不明瞭)、言葉がうまく出てこない(単語が出てこない、言い間違える)、他人の言うことが理解できない。
- T (Time:発症時刻): これらの症状がいつ始まったかを確認し、すぐに救急車(119番)を呼ぶことが最も重要です。
この「FAST(ファスト)」は、脳卒中(脳血管障害の総称)を疑う際の重要なチェックポイントとして国際的に広く知られています。早期発見と早期治療が生死を分けるだけでなく、後遺症を最小限に抑えるためにも極めて重要です。ためらわずに救急車を呼びましょう。
脳幹(のうかん)・小脳(しょうのう)とは?
脳幹は、大脳と脊髄を繋ぐ、生命維持に不可欠な中枢部分です。呼吸、心拍、血圧、体温調節、嚥下(飲み込み)といった、私たちが意識しなくても行われている生命活動をコントロールしています。また、目や耳、顔の感覚や運動に関わる多くの脳神経(全部で12対あります)が出入りする重要な場所でもあります。このため、脳幹に障害が起こると、意識障害、呼吸困難、嚥下障害、複視(物が二重に見える)、めまい、顔面麻痺など、多彩で重篤な症状が現れます。
小脳は、脳の後下部に位置し、主に体のバランス(平衡機能)を保ったり、手足の動きをスムーズに調節したり、運動のタイミングや力加減を学習したりする役割を担っています。小脳が障害されると、まっすぐ歩けない(歩行障害)、手が震えて細かい作業ができない(企図振戦:きとしんせん)、呂律が回りにくくなる(構音障害)、めまいといった症状が現れます。
3-4. 高血圧・低血圧:血圧異常が頭痛や耳鳴りに与える影響
血圧の異常、つまり高血圧(血圧が高すぎる状態)や低血圧(血圧が低すぎる状態)も、頭痛や耳鳴りを引き起こす原因となることがあります。血圧は、心臓が血液を全身に送り出す際の圧力のことで、健康を維持するためには適切な範囲に保たれる必要があります。
高血圧の場合、常に血管に高い圧力がかかっている状態が続くため、特に脳の細い血管にも大きな負担がかかり、頭重感(ずじゅうかん:頭が重く感じる、スッキリしない感じ)や拍動性の頭痛(心臓の拍動に合わせてズキンズキン、ガンガンとするような痛み)を感じることがあります。特に、普段の血圧よりも急激に血圧が著しく上昇した際には、激しい頭痛やめまい、吐き気、視力障害、けいれん、意識障害などを伴う「高血圧緊急症」と呼ばれる非常に危険な状態になることもあり、この場合は迅速な降圧治療が必要です。
耳鳴りに関しては、高血圧が長期間続くと、全身の血管に動脈硬化(血管が硬くなり、弾力性が失われて内腔が狭くなる状態)を進行させ、その結果として内耳への血流が悪くなることで引き起こされると考えられています。「ゴーゴー」「ザーザー」といった拍動性の耳鳴り(血流の音が聞こえるような感じ)が特徴的なこともあります。
一方、低血圧の場合は、脳への血流が十分に確保されにくくなるため、頭痛や頭重感、めまい、立ちくらみ、全身の倦怠感、朝起きるのがつらい、集中力の低下などが起こりやすくなります。特に「起立性低血圧」といって、寝ている状態や座っている状態から急に立ち上がった際に、一時的に脳への血流が不足して血圧が急激に下がり、これらの症状が現れることがあります。
耳鳴りも、高血圧と同様に内耳への血流不足から生じることがあり、「シーン」というような持続的な音が聞こえることがあります。高血圧も低血圧も、自覚症状がないまま進行していることも少なくありません。健康診断などで血圧の異常を指摘された場合は、放置せずに医師に相談し、適切な血圧管理(生活習慣の改善、必要であれば薬物療法)を行うと共に、背景に他の病気が隠れていないかどうかも含めて検査を受けることが大切です。
血圧の正しい測り方
家庭で血圧を測る際は、以下の点に注意すると、より正確な値を得やすくなります。
・測定時間:朝(起床後1時間以内で、排尿後、朝食・服薬前)と夜(就寝前)の1日2回、決まった時間に測定するのが理想です。
・測定前の準備:測定前5分程度は安静にし、会話や飲食、喫煙、カフェイン摂取は避けましょう。
・正しい姿勢:椅子に背もたれをつけて座り、腕帯(カフ)は心臓の高さに合わせます。腕の力は抜いてリラックスします。
・記録:測定した血圧値と脈拍数、測定日時を記録帳やアプリなどに記録しておくと、医師に相談する際に役立ちます。
正しい測定方法を習慣づけることが、適切な血圧管理の第一歩です。
4. 日常生活に潜む!頭痛と耳鳴りの原因となる生活習慣と改善策
頭痛や耳鳴りは、これまで述べてきたような特定の病気だけでなく、私たちの何気ない日々の生活習慣が原因で引き起こされたり、既存の症状が悪化したりすることが少なくありません。
この章では、私たちの日常生活の中に潜む、頭痛や耳鳴りの誘因となり得る具体的な生活習慣をいくつか挙げ、今日からでも意識して実践できる改善策を提案します。
健康的な生活習慣を心がけることは、これらの不快な症状の予防と軽減に繋がる最も基本的で、かつ効果的な第一歩と言えるでしょう。
4-1. 睡眠不足と不規則な生活:自律神経の乱れと症状への影響
睡眠は、日中の活動で疲れた心身の疲労を回復し、ホルモンバランスを整え、そして自律神経のバランスを適切に整えるために、人間にとって不可欠な生理現象です。睡眠時間が慢性的に不足したり、寝る時間や起きる時間が日によってバラバラだったりする不規則な生活を送っていると、私たちの体を活動モードにする「交感神経」とリラックスモードにする「副交感神経」の切り替えがスムーズにいかなくなり、自律神経のバランスが大きく乱れてしまいます。
自律神経は、血管の収縮や拡張、血圧の調整、心拍数のコントロールなどを無意識下で行っているため、その乱れは全身の血行不良を引き起こし、結果として緊張型頭痛や片頭痛を誘発したり、既に抱えている頭痛を悪化させたりする大きな原因となります。また、音を感じ取る内耳の非常にデリケートな血流も自律神経によって精密に調整されているため、睡眠不足や不規則な睡眠は耳鳴りを新たに引き起こしたり、既存の耳鳴りをより強く、不快に感じさせたりすることがあります。
質の高い睡眠を確保するためには、以下のような工夫を日常生活に取り入れることが重要です。
- 毎日同じ時間に寝起きする習慣をつける: 週末や休日でも、平日と大きく生活リズムを変えないように心がけましょう。体内時計を整えることが質の高い睡眠への第一歩です。
- 寝る前のカフェイン・アルコールの摂取を避ける: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには覚醒作用があり、アルコールは一時的に眠気を誘いますが、睡眠の質を低下させ、夜中に目が覚めやすくなる可能性があります。理想的には就寝の3~4時間前からはこれらの摂取を控えましょう。
- 寝る前のスマートフォン・パソコン操作を控える: これらの電子機器が発するブルーライトは、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制してしまうため、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。少なくとも就寝の1~2時間前からは使用を避けるようにしましょう。
- 快適な寝室の環境を整える: 寝室は静かで暗く、自分が快適だと感じる温度・湿度(一般的に夏場は25~26℃、冬場は22~23℃、湿度は50~60%程度が目安とされています)に保ちましょう。
- 自分に合った寝具を選ぶ: 体にフィットし、寝返りをスムーズに打てるマットレスや、首や肩に負担のかからない高さ・素材の枕を選びましょう。寝具が合わないと、睡眠の質が低下するだけでなく、首や肩のこりを悪化させることもあります。
睡眠の質を高めることは、頭痛や耳鳴りの予防・改善だけでなく、日中の集中力や作業効率の向上、免疫力のアップ、精神的な安定など、全身の健康維持にとっても非常に多くのメリットがあります。
メラトニンとは? 睡眠との深い関係
メラトニンは、脳の松果体(しょうかたい)という部分から分泌されるホルモンで、「睡眠ホルモン」とも呼ばれています。メラトニンは、明るい光を浴びると分泌が抑制され、暗くなると分泌が促進されるという特徴があり、私たちの体内時計を調整し、自然な眠りを誘う働きをしています。
夜になっても明るい照明の下で過ごしたり、スマートフォンなどのブルーライトを浴び続けたりすると、メラトニンの分泌が妨げられ、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりする原因となります。寝る前は部屋の照明を少し暗くしたり、暖色系の間接照明を利用したりするなど、光環境を工夫することも質の高い睡眠を得るためには有効です。
4-2. 長時間デスクワークとスマホ:不良姿勢が招く身体への負担
現代社会において、長時間のデスクワークやスマートフォンの日常的な使用は、多くの人にとって避けられない生活の一部となっています。しかし、これらの行為は無意識のうちに猫背や顔が前に突き出るような前かがみの姿勢を招きやすく、首や肩、背中の筋肉に持続的かつ大きな緊張を強いることになります。
このような良くない姿勢が長時間続くと、特定の筋肉がカチカチに硬直し、その部分の血行が著しく悪化します。特に首周りの血行不良は、脳への酸素や栄養の供給を低下させ、頭重感や締め付けられるような痛みをもたらす緊張型頭痛の大きな原因となります。
また、首の骨である「頚椎(けいつい)」は、本来、横から見るとゆるやかなS字カーブを描いており、このカーブが重い頭(成人で約5~6kg)の重さを効果的に分散するクッションの役割を果たしています。しかし、うつむき姿勢が長時間続くと、この頚椎の自然なカーブが失われ、首の骨がまっすぐになってしまう「ストレートネック(スマホ首とも呼ばれます)」という状態になることがあります。ストレートネックも、慢性的な頭痛や肩こり、首の痛み、めまい、手のしびれなどを引き起こしやすい状態です。
さらに、首や肩の筋肉の過度な緊張は、耳周辺の血流にも悪影響を及ぼし、耳鳴りを新たに誘発したり、既存の耳鳴りを悪化させたりする可能性があります。特に、首の筋肉は耳の後ろや側頭部につながっているため、これらの筋肉の緊張が直接的に耳の不調に関わることがあります。
対策としては、まず正しい姿勢を常に意識することが何よりも重要です。デスクワーク中は、以下の点に注意し、体に負担の少ない環境を整えましょう。
- ディスプレイの画面上端が、自分の目線の高さか、やや下になるようにモニターの位置や椅子の高さを調整する。画面を見下ろす形になると首への負担が増します。
- 椅子に深く腰掛け、背もたれをしっかりと使い、骨盤を立てて背筋を自然に伸ばす。足の裏全体が床にしっかりとつくように椅子の高さを調整する。必要であればフットレストを使用するのも良いでしょう。
- キーボードやマウスは、肘の角度が90度以上になるリラックスした位置に置き、肩が上がらないように注意する。手首が反り返ったり曲がったりしないように、リストレストを利用するのも有効です。
- 少なくとも1時間に一度は立ち上がって軽いストレッチをしたり、少し歩いたりするなど、こまめに休憩を取り、同じ姿勢を長時間続けないようにする。遠くの景色を見て目を休ませることも忘れずに。
スマートフォンを使用する際は、できるだけ画面を目線の高さまで上げて持つようにし、首だけで下を向くのではなく、体全体で少し前傾するような意識を持つと、首への負担を軽減できます。そして、歩きスマホや寝ながらのスマホ操作は避け、長時間同じ姿勢で使用し続けないように注意しましょう。
ストレートネックとは? そのメカニズムと影響
健康な人の頚椎(首の骨、7個あります)は、横から見ると前方にゆるやかにカーブしています。このカーブは「生理的前弯(せいりてきぜんわん)」と呼ばれ、バネのように衝撃を吸収し、重い頭部(体重の約10%にもなると言われています)を効率よく支えるクッションの役割を果たしています。
しかし、長時間のうつむき姿勢(パソコン作業、スマホ操作、読書など)や、合わない枕の使用などが原因で、この頚椎の自然なカーブが失われ、首の骨がまっすぐ、あるいは後方にカーブしてしまった状態を「ストレートネック」または「スマホ首」と呼びます。この状態になると、頭の重さが首や肩に直接的に、そして過度にかかりやすくなり、その結果として慢性的な頭痛、頑固な肩こり、首の痛みや可動域制限、めまい、吐き気、手のしびれ、自律神経の乱れなど、様々な心身の不調を引き起こす原因となります。
4-3. カフェイン・アルコールの過剰摂取:頭痛・耳鳴りを誘発するメカニズム
コーヒーやお茶(緑茶、紅茶、ウーロン茶など)、エナジードリンク、コーラなどに含まれるカフェイン、そしてお酒に含まれるアルコールは、適量であれば気分転換になったり、リラックス効果をもたらしたりすることもありますが、過剰な摂取は頭痛や耳鳴りを引き起こしたり、悪化させたりする原因となることがあります。
カフェインには血管を収縮させる作用があり、この作用によって一時的に頭痛(特にズキズキと拍動する片頭痛)を和らげる効果が期待できる場合もあります。実際に、一部の市販の鎮痛薬には、痛みを抑える効果を高める目的で無水カフェインが配合されています。しかし、日常的に大量のカフェインを摂取している人が、カフェインの血中濃度が低下した際に、収縮していた血管が急激に拡張し、その反動でかえって「カフェイン離脱頭痛」と呼ばれるつらい頭痛を引き起こすことがあります。この頭痛は、カフェインを摂取すると一時的に改善するため、さらにカフェインを求めてしまうという悪循環に陥りやすいのが特徴です。また、毎日大量のカフェインを摂取していた人が急に摂取をやめたり、摂取量を大幅に減らしたりすると、頭痛の他に、倦怠感、集中力の低下、吐き気、イライラ感などの離脱症状が現れることもあります。
耳鳴りに関しては、カフェインの持つ神経興奮作用が、聴覚に関わる神経を過敏にし、耳鳴りを感じやすくさせる可能性や、既存の耳鳴りを増強させる可能性が一部で指摘されています。ただし、これについてはまだ明確な科学的根拠が確立されているわけではありません。
一方、アルコールは、摂取すると一時的に血管を拡張させる作用があります。そのため、片頭痛持ちの人がアルコール(特にポリフェノールを多く含む赤ワインや、ヒスタミンを遊離させやすい醸造酒など)を摂取すると、脳の血管が拡張して炎症を引き起こし、片頭痛発作を誘発したり、既存の頭痛を著しく悪化させたりすることがよくあります。また、アルコールには利尿作用(尿の量を増やす作用)があるため、体内の水分が過剰に排出され、脱水状態に近い状態になると、血液の粘度が高まり全身の血行が悪くなるため、これも頭痛や耳鳴りの一因となり得ます。二日酔いの頭痛も、アセトアルデヒドという有害物質の影響や脱水などが複合的に関与していると考えられています。
カフェインやアルコールの影響の受けやすさには大きな個人差がありますが、「最近ちょっと飲みすぎかな?」「これがないとスッキリしない」と感じる場合は、意識して摂取量を控えることが大切です。一般的に、健康な成人の1日のカフェイン摂取量の目安は、マグカップでコーヒー3杯程度(約400mg)までとされています(妊娠中の方や特定の疾患をお持ちの方はさらに注意が必要です)。アルコールは、厚生労働省が推奨する「節度ある適度な飲酒量」として、1日平均純アルコールで20g程度(ビール中瓶1本、日本酒1合、ワイングラス2杯弱に相当)とされています。休肝日を週に2日以上設けるなど、上手な付き合い方を心がけましょう。
カフェインが含まれる意外な食品・飲料
カフェインはコーヒーや紅茶だけでなく、以下のようなものにも含まれていることがあります。摂りすぎを避けるためには、成分表示を確認する習慣をつけましょう。
・緑茶、抹茶、ほうじ茶、ウーロン茶、ココア
・エナジードリンク、栄養ドリンク(多くの製品に高濃度のカフェインが含まれています)
・コーラなどの炭酸飲料
・チョコレート、カカオ製品(特に高カカオチョコレートはカフェイン量が多い傾向があります)
・一部の鎮痛薬、風邪薬、眠気覚まし用の医薬品
知らず知らずのうちにカフェインを過剰摂取している可能性もあるため、注意が必要です。
4-4. 精神的ストレスと過労:心身への影響と具体的なリフレッシュ方法
職場での仕事上のプレッシャーやノルマ、複雑な人間関係の悩み、家庭内での問題、経済的な不安、将来への漠然とした不安など、現代社会は多種多様な精神的ストレスに満ちています。また、慢性的な長時間労働や残業続きで十分な休息が取れないといった肉体的な過労も、心と体の健康に多大な悪影響を及ぼし、頭痛や耳鳴りの大きな引き金となります。
ストレスを感じると、私たちの体は危険や脅威に備えようとして緊張状態になり、自律神経のうち、主に活動や興奮を司る「交感神経」が優位になります。交感神経が過剰に活発になると、全身の筋肉がこわばり、血管が収縮して血行が悪化し、特に首や肩の筋肉の緊張が高まることで緊張型頭痛が起こりやすくなります。また、ストレスは自律神経全体のバランスそのものを乱し、血管の収縮・拡張のコントロールを不安定にさせ、これが片頭痛を誘発したり、症状を悪化させたりすることもあります。
耳鳴りに関しても、ストレスによって自律神経のバランスが乱れると、内耳への血流が悪化したり、聴覚に関わる神経が過敏になったり、あるいは脳が本来気にならないような小さな耳鳴りの音を過剰に意識しやすくなったりして、症状が新たに現れたり、既存のものが悪化したりすると考えられています。実際に、ストレスを感じると耳鳴りが大きくなる、と訴える方は少なくありません。
このようなストレスや過労による心身への悪影響をできる限り避けるためには、自分に合った効果的なストレス解消法(リフレッシュ方法)を見つけ、日常生活にうまく取り入れることが非常に重要です。人によって効果的な方法は異なりますので、色々と試してみて、自分が心からリラックスできるもの、楽しめるものを見つけましょう。
以下に、具体的なリフレッシュ方法の例をいくつか挙げます。
- 適度な強度の軽い運動: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳、ヨガ、ピラティス、ストレッチなど、自分が心地よいと感じる程度の有酸素運動は、全身の血行を促進し、気分転換になるだけでなく、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを減少させる効果があります。週に2~3回、1回30分程度から無理なく始めてみましょう。
- 趣味に没頭する時間を作る: 音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、絵を描くこと、楽器の演奏、手芸、ガーデニング、料理、プラモデル作りなど、自分が心から楽しめることに集中する時間は、嫌なことを一時的に忘れさせ、心をリフレッシュさせてくれます。
- 自然と積極的に触れ合う: 公園を散歩する、森林浴(フィトンチッドという成分にはリラックス効果があるとされています)をする、海辺をゆっくりと歩く、山登りをするなど、自然の中で過ごす時間は、心身をリラックスさせ、ストレスを軽減する効果があると言われています。
- 親しい人との建設的なコミュニケーション: 家族や信頼できる友人、恋人など、安心して話せる相手と会話を楽しむことは、孤独感を和らげ、安心感や幸福感を与えてくれます。時には、自分の悩みを正直に打ち明けるだけでも、気持ちが楽になることがあります。
- リラクゼーション技法の実践: ゆっくりと時間をかけて入浴する(38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分程度浸かるのがおすすめです)、アロマテラピー(ラベンダー、カモミール、ベルガモット、サンダルウッドなどリラックス効果のある精油の香りを楽しむ)、瞑想(マインドフルネス瞑想など)、漸進的筋弛緩法、深呼吸法(特に腹式呼吸は副交感神経を優位にしやすく効果的です)なども、心身の緊張を和らげるのに役立ちます。
- 質の高い十分な睡眠を確保する: 前述の通り、十分な睡眠は心身の疲労を回復し、ストレス対処能力を高める上で非常に重要です。寝る前の準備から睡眠環境まで気を配りましょう。
自分に合ったストレス解消法をいくつか持っておくこと、そしてそれを定期的に実践することが、ストレスと上手に付き合い、頭痛や耳鳴りの予防・軽減に繋げるための重要な鍵となります。
漸進的筋弛緩法(ぜんしんてききんしかんほう)とは?
漸進的筋弛緩法は、体の各部分の筋肉を意識的に緊張させた後、一気に緩めるという動作を繰り返すことで、心身のリラックス状態を導き出すリラクセーション法の一つです。特別な道具も場所も必要なく、比較的簡単に習得できます。
基本的なやり方は、例えば、まず両手に力を入れて強く握りしめ、5~10秒ほど緊張を保ちます。その後、パッと力を抜いて20~30秒ほど脱力し、その弛緩した感覚を味わいます。これを腕、肩、首、顔、背中、お腹、足など、体の各部位で順番に行っていきます。
この方法を実践することで、筋肉の緊張がほぐれるだけでなく、精神的な緊張も和らぎ、不安感の軽減や入眠促進などの効果が期待できます。ストレスを感じやすい方や、不眠に悩む方にも試してみる価値のある方法です。